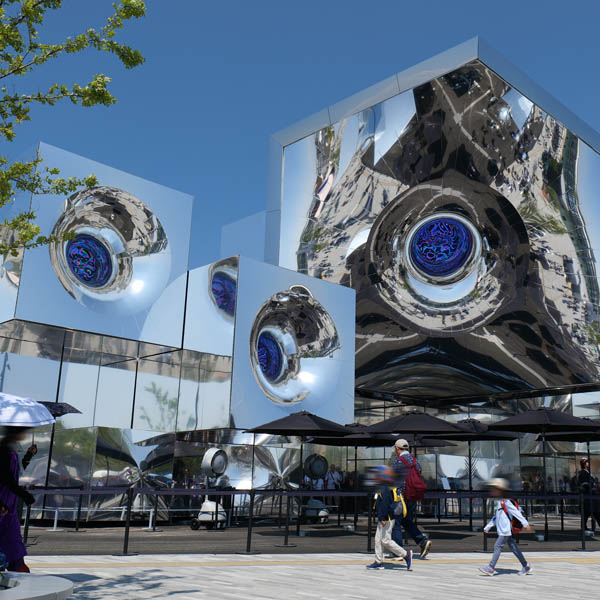アーツカウンシル金沢では、2022年の設立当初から「お届けアーツ」と称して金沢市内の小・中学校、児童館、保育所、認定こども園、幼稚園を対象に、市内で活躍するアーティストを派遣するアウトリーチ活動を行なっている。「伝統芸能」「クラシック音楽」「クラフト」「アート」と要望に合わせたプログラムを選択できるなか、昨年は初めて、小学校に実際に作品を運び入れて、アーティストとともに鑑賞型のワークショップを行なった。
この発展として2025年度に向けて準備中なのが、札幌市が先進的に活動を行っている「アーティスト・イン・スクール」という形式のアウトリーチである。札幌で実践されているアーティスト・イン・スクール(以下、AIS)は、どのような体制・内容で行われているのか。札幌市のアートシーンを担うスポットとして知られるさっぽろ天神山アートスタジオに伺い、現場をよく知る一般社団法人AISプランニングの小林亮太郎氏に話を聞いた。
──まずは、AISを始めた経緯について教えていただけますか。
弊社の代表である漆崇博が、かつて作家として展覧会を開催したとき、アートと社会を繋ぐ場所には人がいないといけないんだということに気づいたことが一つのきっかけです。彼はその後アートコーディネーターとして県外の活動に関わり、学校など余白があるところにアーティストのアトリエがあったら人に見てもらえる状態で制作環境が作れるんじゃないかと考えました。彼が大学院修了を機に北海道に戻りそういう活動を始めようと思ったら、それをすでに始めている人がいて、それがここさっぽろ天神山アートスタジオで今ディレクターをしている小田井真美さんだったんです。
彼女は元々帯広市での国際展のスタッフとして1年程アーティストと協働して、本人たちとしてはすごく良い作品ができたけど地元の人たちの反応がこちらと比例していないように感じ、もう少し接点を作らなければと思ったそうです。そこで考えたのが、人が集まるコミュニティにアーティストが入るというやり方。地方は特に、広いグラウンドで地域の夏祭りがあるように、学校が地区のコミュニティになっていることが多い。そういう文化を知って、2003年に帯広でのアートプロジェクトの中で、小学校にアーティストを送るという企画を実施したのが、今の北海道でのアーティスト・イン・スクールの原型となっています。 当初のアーティスト・イン・スクールは、夏休みの学校をアーティストのアトリエとして活用するという内容でしたが、漆が合流した2004年以降は、学校が通常に運営している期間を含めてアーティストが学校に通うこと、空き教室をアトリエとして活用させてもらうこと、授業に参画しないことを前提に、学校(子ども、教職員、地域住民)とアーティストの新しい関係が構築されていくことを目的した事業として帯広を含む十勝地域でのアーティスト・イン・スクール実行委員会を立ち上げます。
実行委員会が始動し最初に取り組んだ帯広の小学校では、冬休みに保護者が小学校に集まってグラウンドに水を撒いてスケート場を作るんです。そういうふうに保護者も関わりながら、アーティストは子供達にスケートを教えてもらう、代わりにアーティストは子供達に絵を教える。そうした北海道ならではな環境を踏まえた活動が展開されていきました。
この時は新聞社がスポンサーになってくれたのですが、札幌でも同じことやりたいぞと思ったときに「トヨタ・子どもとアーティストの出会い」という事業の委託を受け、その事務局機能も担いました。2006年から数年この事業をやって、さらに続けていくために札幌市の文化行政に働きかけようということになり、当時の行政の文化部担当の方や現場の校長・教頭先生を呼んで小学校の体育館でシンポジウムを開催しました。すると市の担当の方が動いてくれて、補助事業という形で予算を作ってくれたんです。
──札幌AISの特徴を教えてください。
その帯広でのときから、アーティストは先生のように「教えにいく」のではなく、「新しい仲間」「転校生」というポジションです。子供と大人というのではなく、転校生という子供同士の関係性で、授業として入らない。他の地域で実施されているアウトリーチは基本的に授業の枠組みを使うので、先生のOKさえ出れば難しいことはあまりないと思います。趣旨を理解して授業を引っ張れるアーティスト、もしくはコーディネーターがいればできるし、図工の時間だったら文化庁で制定されているコミュニケーション教育事業という枠に当てはめることもできます。うちのような「転校生が休み時間にどこかで何かやってるぞ」というパターンは全国でもほとんどないです。
──アーティストはどのように選定するのですか?学校側からリクエストはありますか?
始めた頃、学校側は「何やるんですか?」という状態なので「こういう感じでやってこうなります」というロードマップを提示し、安心してもらえるゴールを設定していました。先生方も「子供達がこう関わればいいのね」とわかるように。でも最近は学校側が変わってきましたね。
昔の学校は基本的に一つのクラスに何十人もいて、トップダウンで教えるというのが当たり前でした。今は小学校に行くと、クラスから抜け出したりうろうろしたりする子がいて、多様性という言葉によってそのやり方ができない。先生方は一人一人のスタイルを認めてあげながら教えていくというコーディネーターの立場になり、そこから漏れていく子供達はクラスの先生ではなく、保健室の先生や校長・教頭が受け皿になるという体制になってきました。「そういう子たちの居場所になるよね」と、勘が働く先生たちにだんだんと理解が広まっていったんです。
入り口は「アーティストと触れる経験になります」だけど、学校という場所でワイワイやっていると実際、最初にそういう子たちの居場所になります。クラスの図式とは違う関係性ができる、そういう説明をすると、先生方も「それが欲しいんです」と仰ってくださる。演劇でも絵でも、コンテンツについては先生も詳しくないから「そこはお任せします」という感じです。
毎年3校の枠があって、2人は地元の作家さん、もう1人は県外・海外といった感じで決めています。弊社と関係はあっても札幌に縁のなかった人を呼ぼうということで、例えば天神山アートスタジオでレジデンスするアーティストや、先ほど言ったトヨタの事業のネットワークで関係ができた方、札幌国際芸術祭に関わってくれた方などに声をかけてきました。美術系が多いですが、作品の有無というより創作活動さえあれば成立しますね。
向いている気質としては、レジデンスのように普段とは違う環境、学校という新しい環境で楽しみながら制作できることと、少なくとも子供を嫌いじゃない人(笑)。単純に、アーティストにとってストレスになりますから。状況が状況だけに「子供のため、先生のため…」とか気になるかもしれないけど、まずそこはあまり考えないで好きに滞在していいよと伝えています。「おーいみんな〜」とかって先生らしく呼びかけられるような性質は必要なくて、ドキドキしながら学校に来て子供と一緒に驚き、発見し合って進めていける人が向いていますね。やり続けていると必ず途中で何か見つけられる、そういう偶発的なものも最近は大事にしています。
──これまで活動されてきて、手応えを感じた瞬間はありますか?印象的だったエピソードなど教えてください。
子供達が人生で出会わない人に出会える、というのはまずあります。先生じゃないというポジションがすごく良い。小学校に入った時にまず教えられるのって「小学生」と「先生」という関係の上での社会の振る舞い方だと思うんです。話し方とかですね。でも我々はそれとは関係なく入っています。「え、同じ大人なのにそこは普通に話していいんだ」「何やってるかよくわからない人がいる」という経験って、昔は学校の外で補っていたと思うんだけど、今それはできない。学校の外の知らない人は全員不審者扱いですからね。となると、子供達の世界の大人は親か先生か塾や児童館の先生、10人くらいしかいなくて、それは非常に危険です。それ以外の大人もたくさんいますから。だから、安全によくわからない人たちとつながれる、という経験がまず一つの価値だと思います。
それで、どの学校でも数百人の子供のうち、必ず誰かに響くんです。例えば、鉄の溶接を行うアーティストが来たときに、その作業を学校でやったら面白いねということで図工室の窓に板を貼って、子供達がそれを覗ける状況を作ったことがありました。その作品を展示したときに、僕はコーディネーターとしてずっと彼女と一緒にいるから彼女を一番理解できてると思ってたけど、パッと男の子が入ってきて「この作品てこういうことですよね!」と話しかけてきたんです。僕はその子が何言ってるかわからなかった(笑)。でもアーティストは「そうそう!」って会話が成り立ってて、「あ、理解じゃなくて、共鳴しちゃうんだ」と。自分を超えたところで理解し合うということがありえて、「こういうことのためにあるのか」と思いましたね。学校だとどうしても軽く「すごかったね〜」という感想で終わりそうだけど、年齢関係なくアーティストがやりたかったことをバシッとキャッチできる子が少なからず小学校にはいる。そういう、まさに雷に打たれたような衝撃を受ける子の存在は、はたから見ていると爽快ですね。
──何百分の一かもしれないですけど、そういう機会を作り出せるのは感動的ですね。
子供はそんなふうにわからないものに対して近づいていける一方で、大人はなかなかそれができないものです。先生方の中には「なにこれ」「理解できないからいいわ」と自分の世界から消そうとする人もいました。わからないことに対してストレスを感じるんですね。でもやっぱり教育者だから、子供達がすごく楽しんでるからすごく面白いのかもしれない、そういう理由でこの活動はいいと思いますと言ってくれる先生も中にはいる。もう少し入りこんでくれる先生だと、おもしろいし子供達も飛び込んでる、じゃあ俺も!って一緒に飛び込んでくれます。そこがこの事業の一番いいところで、子供達は色々経験できるけど、結局はそれを受け入れようとする大人が変わらない限りはこういう取り組みは続きません。何十校とやってるうちに、前までは先生の伝手をたどって「やってくれませんか」とお願いしてきたんですけど、もう20年くらいやっているので、今は過去に経験した先生たちが「やりたい」と連絡をくださるようになりました。
その状況はとてもやりやすくて、我々は何十校もやってるから経験と知識はあるけど、外部の人間ができることって100点満点にはならないんですよね。学校側で同じように賛同してくれて学校側のコーディネーターになってくれる先生がいると、100点、それ以上の可能性が出てきます。今まででいうとアーティストが作品を発表する中庭の空間で、先生方が盛り上がって集まり音楽会をしたことがありました。また校長先生の主導で校庭に雪山を作り、地域の人の協力でそこに花火を仕込んで花火大会が開かれ、それが今でも続いていたり…と。我々が入ることによって、先生方が「これしかできない」と思ったことを拡張しているという感覚というか、先生方が責任を持つことで本気になると、始めたときには予想していなかったことがなんでも出来てしまいます。
──先生方にとっても、とても刺激的な経験になっているんですね。小林さん自身はコーディネーターとして、作家の紹介以外にどのような役割を担っているんですか?
毎回必ずアーティストと一緒に学校に行きます。授業時間以外も学校をうろうろしながら作家と同じスタンスで行動するんです。転校生形式だと、アーティストは気持ちが迷ったりグニャグニャしたりすることがあるので、安心してもらうために一緒にいるようにしています。やりたいことがあったときには僕が先生に聞いてくるとか、アーティストと学校の間にうまく入るためにも。
図工の授業の見学に行かせてもらうと、先生から「一コマ空いてるんで一緒に何かできませんか」という話になることもあります。そうなると授業でも関わるし休み時間も子供が来てくれるし活動がどんどん回っていくので、あえてぶらぶらしたり先生に話しかけたりして接点を作りにいっていますね。
──アーティストの援護部隊のような存在かと思ってたんですが、ずっと帯同しているんですね。
援護というか僕たちが最前線にいないと、基本的にアウェイの環境なのでアーティストはきついと思います。授業の場合でもコーディネーターというポジションだからと言って一歩引かず、アーティストと同じラインにいる状態にしておきます。どうぞどうぞというやり方もあるにはありますが、子供達からするとその距離感は関係ないわけで。アーティストのことが好きになる子もいれば自分に懐いてくれる子もいたり、それぞれに友達ができて活動が大きくなっていく。アーティストにも学校にも、そういう活動であることを理解してもらうことが大切です。
──短い時間でしたが、お話を伺ってAISの本質を理解できた気がします。本日はありがとうございました。