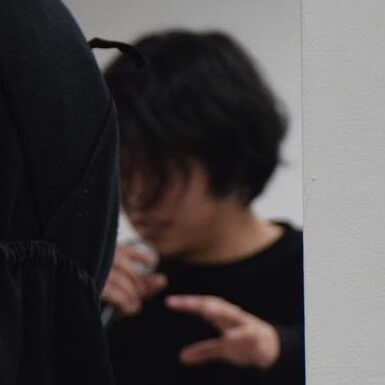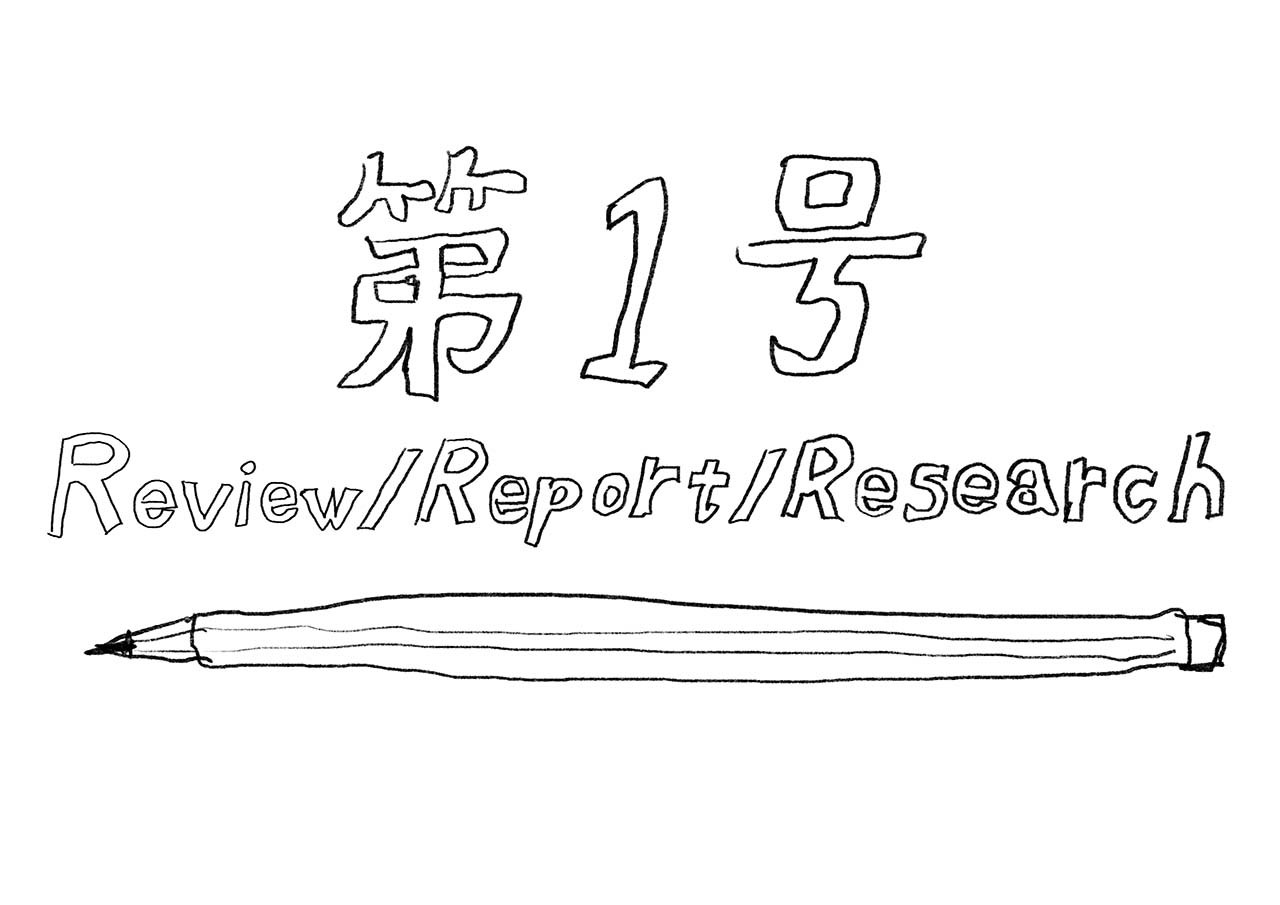
みなさん初めまして、宮崎竜成と申します。私は石川県金沢市を拠点に活動する現代美術のアーティストです。かれこれ、金沢に来て12年目を迎えたのですが、芸術活動を行いながら12年間を金沢で過ごしているとさまざまなアートシーンの移り変わりが見えてきます。特に金沢は文化都市として公共的なものからオルタナティブなものまで、さまざまな施設やイベントが醸成される場所です。こうした金沢のイベントやそれに関わる人々、場所等を、Review(内容を深掘りする)、Report(広く発信する)、Research(魅力を発見する)という「3つのR」の観点から執筆する各月連載を開始します。
第一回目は、2025年上半期(1〜6月)までの間で開催されたアーティスト自身が作る展覧会のReportです。
そもそも、アーティストはどのように活動を行っているのでしょうか?ギャラリーに呼ばれて作品を展示し、作品がバンバン売約される! 美術館や他の公的施設で華々しくデビュー! …もちろんそうした側面もありますが、全てのアーティストが常にこうした機会を持つわけではありません。アーティストのキャリアは、アーティストが作り続けた作品を自分自身で発信する、「自主企画」での展覧会が活動の大きな要素になっていると言っていいと思います(もちろん各々のアーティストによって一概に言うことはできませんが…)。それはコミュニティの繋がりでどこかのスペースから企画を依頼されることもあれば、誰に頼まれるでもなくアーティスト自身によって持ち込まれる(あるいは会場を用意する)場合もあり、キュレーターが企画するのでも、ギャラリーで販売するのでもない、固有の生態系や方法論で展開され、美術館やギャラリーで行われている展覧会よりも実験的な実践や、アーティストの興味、あるいは社会の同時代性を生に映し出すこともしばしばです。そして、金沢では、こうしたアーティストの企画と並走し、協働しながら独自のネットワークを構築するようなスペースも増えています。前置きが少し長くなりましたが、今回は、(主に若手アーティストによる)こうした展覧会を、展示スペースと共に紹介します。
1. 沖田愛有美 個展「暦を運び、種を食く」
会場:白鷺美術
漆絵作家である沖田愛有美さんによる個展。白鷺美術が主催となって開催され、沖田さんが展示の内容を構成しています。会場である白鷺美術は、作家、アートディレクターでもある巽勇太さんが運営しています。一階がBarとなっており、2階に上がると、白く塗られたホワイトキューブ空間が広がっています。普段は巽さんによる企画展示や演奏会が行われています。また、一階、階段、二階に至るまで、照明がこだわり抜かれており、繊細な色調と明暗のコントラストが、魅力的な空間を演出しています。
沖田さんは漆を描画材料として絵画を制作しており、自然の営みのリズムやそれを生きる私たち人間の制度など、自然(非人間)と人間との関わりがテーマとなっています。今回の個展では、農耕とその営みを貫くリズムとしての暦、そしてその営みに潜む信仰をモチーフとした作品群が並んでいます。特に象徴的なのは比較的どの作品にも登場する「鳥」たちです。それぞれの絵画の中で、鳥は植物と戯れ、稲を啄み、巣を作り、卵とも太陽とも取れる白色の球体と共に描かれます。古代の日本や中国では鳥と稲作が強く結びついており、雨の気配を察知し、鳴き声を鳴らす翡翠(かわせみ)の習性に着目し、翡翠の鳴き声を模した雨乞いの儀式を行ったり、逆に太陽を運ぶ者としての鳥への信仰を持っていたりしていました。稲作は太陽を基準とした太陽暦を基準として営まれ、また晴れや雨といった天気も、太陽の移り変わりによる季節の変化と結びついています。それら自然のリズムと、それに向き合う人間との関係を媒介するようなものとして鳥の存在があると言えるでしょう。
沖田さんによれば、絵の中に描かれた白い球体は、太陽でもあり、餅でもあるそうです。本展示が年末から元旦をまたいで開催されたこともあり、餅は暦の大きな節目としてのイメージも含まれているのでしょう。また、会場には絵画だけでなく、実際の稲も展示されています。自然と人間の接点を探る沖田さんの制作は、それを表現する素材である漆と沖田さん自身との関係の写鏡であるとも言えます。人間が操作し切ることができない漆自身の変化に委ねつつも、沖田さん自身の判断で筆を運ぶ、こうして生まれた筆のストロークと艶のある黒い画面、そして会場の照明とが交わることで浮かび上がる世界がそこにはありました。


2. 金保洋・菊谷達史「木について」
会場:SKLo
漆芸作家である金保洋さんと、絵画・アニメーション作家である菊谷達史さんによる2人展。会場であるSKLoは普段はオーナーである塚本美樹さんやスタッフによる企画展が定期的に開催されていますが、本展示は職場の(元)同僚である2人の常日頃の会話が深まることによって生まれた企画をギャラリーに持ち込むことで開催されたことが、菊谷さんのSNSの発信によって説明されています。お互いの異なる視点から「木」にまつわる歴史を手がかりに、作品だけでなく、その作品を生み出すための材料そのものも分け隔てなく展示するものとなっています。
金保さんは、漆芸の材料であるウルシの木やその近種の実であるハゼの実を展示しながら、ウルシの木そのものの美映えの魅力や歴史、流通などを掘り下げることで、「木」自体の価値を再定義するような展示構成をとっており、その横で漆独特の艶や色彩が輝く抽象的な造形や、用途や機能を持った器などの自作を並べています。
菊谷さんは、油絵を描く際の溶き油であるテレピンの材料である松の木に着目し、実際のテレピン油を画家のアトリエを再現するかのように展示しながら、松の木の植生や循環サイクルなどに思いを馳せることのできる版画やドローイング、ブラウン管テレビでのアニメーション、そこで流れるレクチャー音声などの作品を展開しています。
2人に共通するのは作品の手前にある材料としての「木」自体への興味であり、「木」に潜むさまざまな物語を拾い上げることで、ものを生み出すアーティスト自身の創造性が、作品を生み出すために扱う素材への向き合い方と切り離すことができないのだと言うことを強く喚起するような展示構成となっています。なぜ油絵で描くのか、なぜ土を使うのか、なぜ漆を使うのか、正直、あまり考えなくて済むことでもあるかもしれません。しかし、良くも悪くも、材料にはそれが使われるようになった歴史があり、その歴史の積み重ねや価値判断の変遷が、今の表現の形を作り出していると捉えることもできるでしょう。
会場となっているSKLoは別エリアでアンティークショップも営んでおり、今回の展示で使われている什器もほぼ全てが木造の古道具で構成されています。また建物自体も木造の町屋となっており、木という素材が持つ性質や歴史に思いを馳せることによって、その造形的魅力を発見できるような空間となっています。こうした空間と展示とが合わさることによって、木をめぐるある種の上演的な雰囲気を醸し出していました。
また、会場は昔、森忠商店という問屋だったそうで、そこでは漆や(明治維新後は)食用、松明用の油を売っていたようです。それが理由で展覧会が持ち込まれたわけではなく、あくまで偶然であったと作家からお聞きしたのですが、木から分化した媒体である漆と油をめぐる展覧会が、本会場を媒体として行われたことには営みの循環のようなものを感じます。




3. 大倉千宙 個展「up side warming down」
会場:6号室
金沢美術工芸大学の大学院で鍛金を学んでいる大倉千宙さんによる個展。会場である6号室は、オーナーの神野元次郎さんが金沢市長町のアパートの一室を借りて営んでいる本屋であり、内装は頼安ブルノ礼市さんによって設計されています。室内では、神野さんにゆかりのある人々による選書が並んでおり、本を通して、さまざまな人となりや思考のかけらに触れるようです。また6号室はレンタルスペースとしても開かれており、今回の大倉さんの展示もこのレンタル利用によって開催されていました。
大倉さんの作品は銅(Copper)を叩いて成形する鍛金技法で制作されています。金属は、工芸及び工業製品に広く用いられますが、その歴史からみても、工芸や工業は実際に手に取って使うという側面があるがゆえに、材料の性質とそこから取りうる加工方法との関係が見た目の美観において非常に重要になってきます。こうした材料と加工の関係によって、今日の日用品もデザインされているといえるでしょう。大倉さんの作品はそうしたことに強く、かつしなやかに着目したアプローチがとられています。例えば展示されているある作品では作品に小さな穴が沢山開けられています。大倉さんによると、銅によって空間が密閉される形態を溶接によって作りたい場合、溶接の熱によって中の酸素から引火しないよう空気の逃げ道としての穴を開けておく必要があるそうです。
大倉さんの作品は、給湯ポットや自宅の風呂桶、器など、手の届く範囲での日用品がモチーフとなっています。しかし、前述した銅の加工の過程で必要となる溶接や穴あけ、スケールの縮小などによって、見た目は見慣れた日用品の形をしているものの、実際に使うことのできないものとして仕上がっている作品が多々あります。こうした、工業的、工芸的な技法に真正面から取り組みつつも、その技法によって生まれてしまう見た目と機能のギャップが、何か愛くるしい存在感を放っていました。6号室の会場に合わせた低い位置に飾られていたこともその存在感を作り出す一旦になっていたと思います。


4. 小野直也 個展「アーティストインレジデンス成果展示」
会場:金石町家(仮)
金沢美術工芸大学の油画専攻で学んでいる小野直也さんの個展。会場となる金石町家(仮)は加賀建設株式会社が運営しており、町家を改装したコミュニティスペースとして、多種多様なバックグラウンドを持つスタッフたちによって活動がなされています。コミュニティスペースでは、飲食の提供や、レンタル、コワーキングの提供のほか、スタッフ企画だけでなく、町家に参画する企業やアーティスト、金石に暮らす人々に至るまでのさまざまな人々によるワークショップやイベントなどが行われており、地域の大人から子供までが訪れる場所、そして訪れるさまざまな人の思いを実現する場所となっています。また、月に一回のマルシェイベントも行われており、そこでは一同にさまざまな企画を楽しむことができます。まさに、地域の居場所となりながらも表現の発信となる、そしてその双方が交わることのできるスペースです。こうした町家のスペースでは、イベントのほか、レジデンススペースとして利用できる比較的広いスペースがあり(以前には金沢美術工芸大学大学院の日本画専攻を修了した乙部亮さんが、2024年に滞在制作と展示を行っています)滞在制作への意欲があった小野さんと、町家のスペースが協力する形で、今回の滞在制作及び成果発表を行っていました。
小野さんは、以前から風景画の制作を継続しており、素早い筆致の積み重ねによって作られる写実的な画面が特徴的です。そして、ただ写実的なだけではなく、現場の空気、気温、湿度などを一息に閉じ込めるような質感を見ることもできます。今回の滞在制作では、3枚の大きなキャンバスにて金石の海を大胆に描き出しています。3枚のキャンバスは連結すると一つの大きな海及び砂浜が浮かび上がりますが、それぞれのキャンバスに描かれる時間帯は、それぞれ異なっています。それは、小野さんが実際の海まで赴き、大きなキャンバスに向き合う中で、時間の移り変わりとそれによって現れる海の姿が刻一刻と変化する姿を直に体感するからこその表現なのではないかと想像します。日本海独特の押し寄せる波、光の反射、砂浜の湿度、そうした変化の機微を捕まえることが現地で描くことの醍醐味であり、また、金石町家(仮)の広い受け皿によって気軽に金石での滞在制作を行えることもまた一つの醍醐味であるように思います。
また、今回の成果発表に合わせて、金石町家(仮)の運営ならではのさまざまなコンテンツの集まるイベント「カナイワのハマ」も開催され、金石町家(仮)の運営ならではの賑わいが作り出されていました。


5. 橋本充智 個展「発生するあなた」
会場:夜喫茶 よふ葉
油絵作家である橋本充智さんによる個展。会場のよふ葉は夜にお茶やお酒が楽しめる夜喫茶となっており、アンティークの古道具や家具に囲まれた隠れ家のような空間となっています。そして、こうした夜喫茶を営みながら、時折、店主の浅井かをりさんと作家とが協働して展覧会を行う会場としても運営されていました(残念ながらよふ葉は2025年6月18日を最後に閉店することになりました)。
橋本さんは、身近な生活で見られる植物や雑草を超近視眼的な視点で描き出す作家です。今回の個展では、隠れ家のようなよふ葉の空間にひっそりと佇むように、植物を描いた小作品が飾られています。植物にクローズアップすることで、普段の生活の視点では見えない葉の絡まり合い、茎のしなやかさ、花が開くエネルギーなど、ミクロな生の物語を、その形から見ることができます。橋本さんはそうした植物の動的な動きを丹念に描き出し、また油絵の画溶液による独特のツヤや、反対に乾燥した画面によって、形だけでなく植物の湿度や気候、匂いまでその生の物語を予感させるように描き出されています。
また、室内に置かれた作品は入り口から奥の部屋に行くに従い萌芽の頃から散り際までの様子が順に描かれており、その作品の合間に(あるいは寄り添うように)木の枝に付けられた越冬するイラガの蛹とアゲハチョウの蛹の抜け殻の作品が展示されています。作品の中だけではなく、作品を鑑賞する時間を通して、植物の生の移ろいを追いかけるような構成となっています。
会場のよふ葉は閉店しましたが、同場所はまた別の使われ方をする形で引き継がれていくそうで、もしかしたらうまくタイミングや条件が合えばまた展覧会などが行われるかもしれません。それについては確証がある訳ではないので、続報を待ちたいと思います。


6. 磐木絵馬 個展「あなたの肌の記憶をたどりにいく」
会場:キタイッサカの土間
金沢美術工芸大学の油画専攻で学んでいる磐木絵馬さんによる個展。会場のキタイッサカの土間は、陶芸家の四井雄大さん、堀江たくみさん、アートディレクターの上田陽子さんと、不定期で入れ替わる居候メンバーによって構成されているシェアハウス&アトリエです。一階の入り口が比較的広めの土間となっており、そこでお酒を飲みながら金沢のアーティストが集まったり、県外から来たアーティストを招いた宴が開催されたり、対外的なイベントやフリーマーケットを行ったり、陶芸教室を開いたりなど広くも狭くもコミュニティの拠点となっています。その一環で、キタイッサカの人々と親交のあるアーティストが展覧会を開くこともあり、今回の磐木さんの個展もそうした繋がりから開催されています。
今回の展示では、瀬戸ノベルティという愛知県瀬戸市を中心として製造された磁器製の人形にまつわる映像作品が展示されています。磐木さんはとあるきっかけで瀬戸に赴いた際に購入した瀬戸ノベルティに関心をもち、その歴史を辿っていくと、その製造元の会社のオーナーが石川県にもゆかりを持っていたことを知った磐木さんは、購入した瀬戸ノベルティを抱え、実際にその製造元(現在は廃業)の元社長へインタビューに伺います。映像作品では、瀬戸ノベルティを持つ盤木さんが愛知県の瀬戸から石川県まで電車で移動する様子が映し出されており、その映像に合わせて、インタビューの音声がノーカットで流されています。土間スペースの机には関連冊子や資料が並べられており、コミュニティスペースとしての居心地の良さも相まってゆっくりと作品のテーマについて知ったり、考えたりすることができます。作品自体は、瀬戸ノベルティという陶磁器産業が西洋を発祥とする造形の模造品として栄えたという事実が、「真正」と「模造」、「中心」と「周辺」という二つの関係を色濃く写しつつめ、その相互の関係を転倒させるように作られています。磁器の艶やかな肌(表面)に一体どういった制度的条件が潜んでいるのか、それを西洋批判でもなく、オリエンタリズムでもない、ただその成り立ちをなぞることで解きほぐされるものがあるのだと思います。
また、本展で特徴的だったのは、展示会場で洋食器による紅茶が振る舞われたり、日本の洋食器を販売する金沢エムザ(百貨店)を見に行ってみるイベントや、洋食器を用いた西洋文化であるアフタヌーンティーをしながらおしゃべりをするイベントなどが開催されているという点です。いわゆるトークイベントだけでなく、こうしたコミュニケーションを通して、アーティストと観客の区別なく、共に知り、共に意見や情報を交換するという時間が生まれます。しかも、それが良い意味でアットホームである(つまり、無理に公に開かないということ)というのが特徴です。それはキタイッサカのもつコミュニティの場があるからこそ生まれるものであり、その緩やかな開かれと閉じられの場だからこそ醸成されるものがあるのだと思います。



7. 番外編:北陸アートビオトープ
こちらは展覧会ではなく、LINEというコミュニケーションアプリを利用した情報プラットフォームであり、先ほども取り上げたアーティストの菊谷達史さんを中心とした管理人によって運営されています(私も管理人の1人として少し関わらせていただいています)。内容は、北陸で開催されるイベントをかなり網羅的に調べ、主に菊谷さんを中心にそのイベント情報をチャットに投稿していくものであり、情報発信の投稿は、管理人だけでなく、そのグループに入っている人全員が行える方式となっています。今では100人以上が参加し、自主企画から公的イベント、ジャンルも美術、音楽、演劇など多岐にわたっています。今回、アーティストによる(主に)個人規模での発信や開催をベースとしたものをいくつか紹介しましたが、この北陸アートビオトープのグループに参加すれば、多様なイベントを網羅的に知ることができます。もし今回の連載で興味を持っていただけた方はぜひ、WEBで検索して参加いただければと思います。
おわりに
今回は第一回の連載としてアーティスト自身が内容を企画する展覧会についてレポートしました。紹介した全てが、いわゆる「ホワイトキューブ」空間ではなく、街の中でギャラリーとしてだけではない活動や運営が行われる場所であり、空間も、その運営に合わせた歴史や時間を纏ったものです。だからこそ、こうした場所とアーティストの作品とが交わることよってこそ生まれる経験が、アーティストにとっても、観客にとってもあるのだと思います。そしてそういった経験の時間が、独自のコミュニティやネットワークを築いているのでしょう。今回は、私の見渡せる範囲として、金沢美術工芸大学の関係者、しかもとりわけ油画をベースに学んできた(いる)人の紹介に偏ったものにはなってしまいましたが、今後の連載では、1年間を通してより多様な表現技法を学んだ方々や、音楽、演劇など他のジャンルの方々の活動についてもさまざまな角度で発信できればと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。