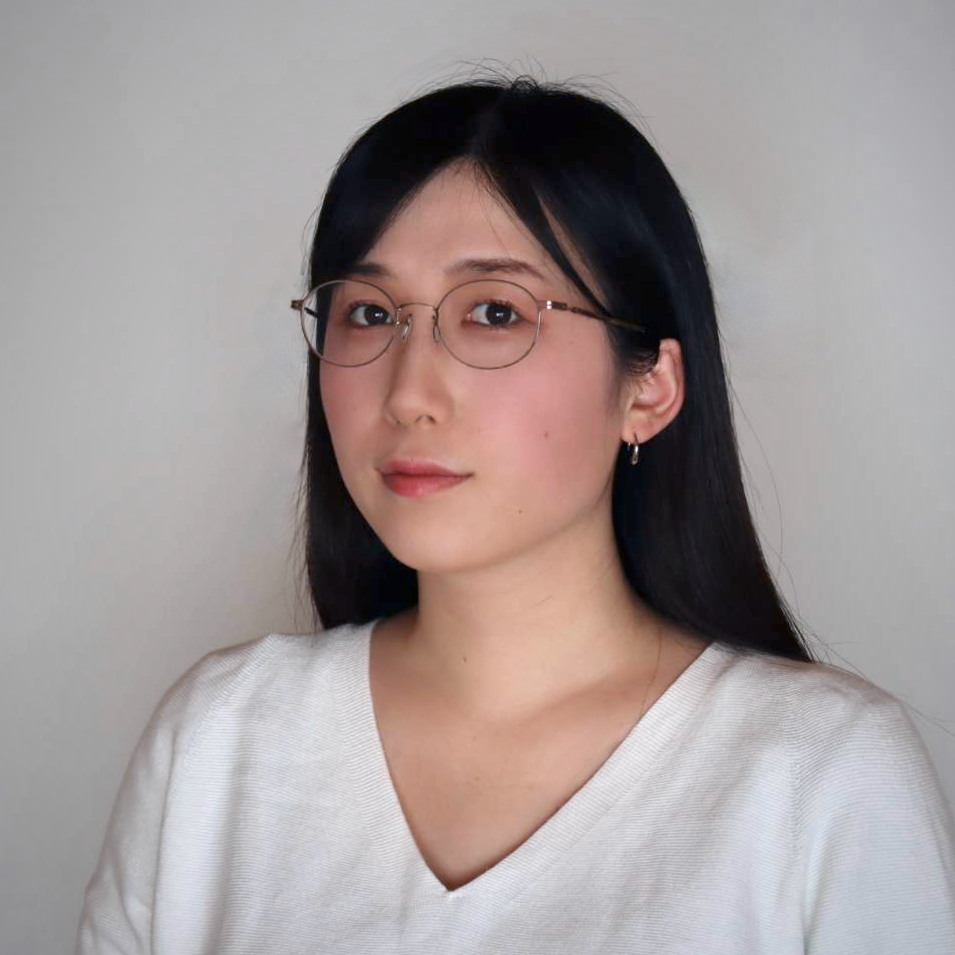金沢美術工芸大学(KANABI)から最新のトピックをお届けする「KANABIカッティング・エッジ」。第15回となる今回はこの春、金沢美術工芸大学の博士後期課程を修了し、同学の油画専攻で実習助手として働きながら、漆の絵画作品の制作を続けている沖田さんからのエッセイです。
私はこの春、金沢美術工芸大学の博士後期課程を修了し、現在は、同学の油画専攻で実習助手として働きながら、漆の絵画作品の制作を続けています。10年間の長い大学生活を終えて、美大が私にとってどのような学びの場であったのかを自身の視点から振り返ってみたいと思います。
1. 美術大学で学ぶこと
このコラムを読んでいる皆さんは、美大の大学院と聞いてどのような場所を想像されるでしょうか。美大に修士課程や、博士課程があることに驚かれる場面にもしばしば遭遇します。また世間的には「アートには実用性があるのか」とか、「アーティストが追求するのは自己表現だ」とか、様々なステレオタイプも耳にすることがあるのではないでしょうか。
とはいえ、こうした問いかけをしている私自身も、田舎町で高校生までを過ごし、何なのかもよくは知らないけれど、きっと面白い世界に違いないと思い美術大学にやってきた一人でした。アートの社会的意義や有用性を真面目に考えるというよりは、社会に出た後も何らかの形でもものづくりを続けていきたいと朧げに考え、とにかく良い作品を作るぞ、という意気込みで学部生時代を駆け抜けました。
ちなみに、私の金沢美大での変遷を振り返ると、学部は油画専攻を卒業し、大学院の修士課程(博士前期課程)では工芸科に進みました。その次の博士後期課程では、工芸から一転し再び絵画領域(油画コース)に戻る、というように紆余曲折を経ています。
絵画の領域と工芸の領域を行ったり来たりしたこの経緯には、学部2年生の終わりに漆の絵画と出会ったことが深く関わっています。
2. 漆の絵画との出会い
2015年は金沢美大と中国北京にある清華大学美術学院との交換留学がいよいよ始まるという年でした。当時学部生だった私はその噂を聞きつけ、油画の指導教員から清華大学美術学院の作品集を借りました。そこで、偶然にもまるで油絵のような漆の絵画に出会います。「漆で絵が描けるんだ」という衝撃から、漆画と呼ばれる漆の絵画を自分でも制作するようになりました。
コラムのはじめで触れたように、私は「なぜ美術大学に入ったのか?」という問いに対して、明確な目的や目標を持っていたわけではありませんでした。しかし、美大の環境はさまざまな刺激に溢れ、特異なものを尊重する場であり、学生一人ひとりが自分にとって特別な何かを見出し、それを軸に目的や目標を打ち立てていくプロセスを全力で支援してくれました。私の場合、その特別なものが漆画との出会いであり、油画に在籍しながら工芸を学べる選択授業に出たり、海外の大学との交換留学プログラムに参加したりと、幅広い経験を通じて自分の興味を深く掘り下げることができたのです。
現在金沢美大には、他領域に開かれた共通造形工房が開設され、領域横断的な制作に対してはより柔軟に対応が可能になっています。

3. 作り手であり研究者であること
学部時代、私は漆画をつくることを全身全霊で楽しんでいました。しかし、より専門的な漆の技術や知識を得たいと考え、大学院では工芸科へ進学しました。そこには思いがけない壁が待ち受けていました。
突如として、「漆画とは何か?」という制作の根幹に関わる問いを突きつけられたのです。この問いには、一見単純に見えて常に複雑な要素が絡み合っています。例えば、日本では明治時代以降、「美術」という概念が導入されてから、工芸と絵画は相反する性質を持つジャンルとして確立されてきました。そのため、絵画と工芸の両方の技術を身につけた私の作品は、絵画の専門家には「装飾的で工芸的すぎる」と映り、工芸の専門家には「絵画的すぎて、漆らしさがない」と評されるという、ジレンマに陥ったのです。
私はどんどん漆画がわからなくなっていきました。これまで夢中になっていた制作の一歩手前で立ち止まり、自分のやっている表現が何であるかに自信が持てず、創作活動が停滞することもありました。しかし今振り返ると、これこそが美大の大学院という場にとっては重要な視点だったのだと理解できます。
学部時代の私は、やってみたいと思ったことにすぐさま挑戦し、それを拡張させていくことに熱中しました。面白いと思ったことはやってみる!と、ものづくりに対しては積極的な姿勢でいました。ただし、大学院ではそればかりではなく、自己表現の開拓や技術力の向上と共に、美術の歴史や制作理論、社会との接続といった観点から課題を見出し、自己を客観的に分析する研究者の視点が求められるようになりました。
作り手として制作物に情熱を注ぐ視点と、客観的に表現それ自体に「なぜ?」と問いかけ続ける研究者としての視点、これらを両輪となすことを、美大の大学院の入り口で学びました。

4. 博士論文の執筆を経て
私は修士課程の2年間で、ものづくりと並行して、その背後にある歴史、概念、理論の探究にも熱中していきました。そして、自分なりの言葉で問いかけに応じられるようになってきた手応えを感じながらも、「漆画とは何か?」という根源的な問いに対する納得のいく答えを見つけ出すには至っておらず、博士後期課程で研究を続けることを決めました。
博士入学の2020年は新型コロナウィルスの流行に見舞われました。緊急事態宣言の発令により大学のアトリエから離れざるを得ませんでしたが、オンラインで熱心な論文指導を受けながら、学術的な知識の蓄積に集中しました。作品制作のみならず、文献や資料の収集、学会発表への挑戦など、修士課程に続く博士後期課程には、学術的な方向にもより一層じっくりと腰を据えて取り組むことのできる環境がありました。
4年間がかりで執筆した博士論文では、修士時代から考え続けていた問いに対する自分なりの答えがようやく見出されました。またこのとき「漆画とは何か?」という問いを、研究を始めた当初の想定よりも幅広く多様な観点から掘り下げることができたことで、「漆画」の概念は当初の認識よりも拡張され、制作の幅もぐっと広がりました。
博士課程の学びでは、幅広い芸術理論や、哲学、社会学的視点に触れることで、実践を振理論と結びつけ基礎体力を養うことに重きが置かれていました。ここで意味を持ったのは難解な書物を読み理論を蓄積することそれ自体ではなく、手を動かして得られた経験を基に、思考と行動を繰り返しフィードバックさせるプロセスの存在であり、それが思いがけない成果をもたらしたのだと振り返ります
博士課程を通じて継続した「問いを立て、それを追求し続けるための筋トレ」によって、今後芸術の道を進むうえで、また他の分野においても、確かな財産となる体力や筋力がもたらされたことは自身にとって学位以上に大きな収穫であったと言えます。

5. 最後に
このコラムでは私の体験をもとに大学院での学びの一例を紹介しました。
学部に続く大学院では、目的を定め論理的に考える研究者の視点が加わることで、はじめに触れたアートの社会的意義や有用性といった目的意識に対する比重が大きくなったようにも見えるかもしれません。一方で、私はあくまでも実践と理論の相互影響が大学院での学びの要だったと考えています。
金沢美大には「手で作り心で考える」という理念があります。大学院で得た知識や理論は、目的や効率の追求のためのみにあるのではありませんでした。手を動かすことも含めた研究活動のプロセスのうちに得た知見や感覚、共感性などにも意識を払うことで、学問や研究の分野にも固定観念にとらわれない新しい知識や概念の形成がなされるのだと、博士論文の執筆を通じて実感しました。
目的までのプロセスを重視することは、予期しない発見や創造が生まれる余白を残してくれます。それは人々の感情とも共鳴することが可能となるような芸術の役割を体現するようなものであったように思います。作り手の視点と研究者の視点、実践と理論の両輪でバランスをとりながら進むことを学んだ美大の大学院での時間は、これから先もきっとものづくりを続けてゆく私にとってかけがえのないものとなりました。